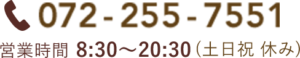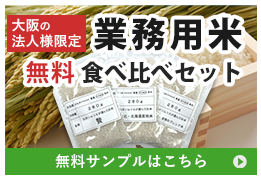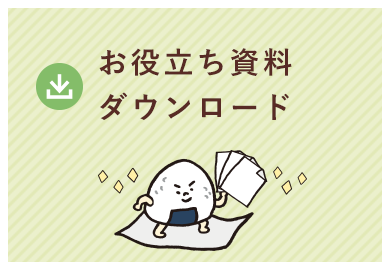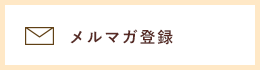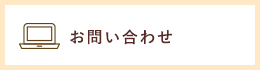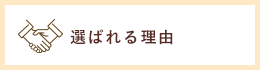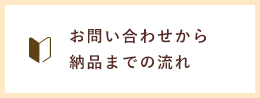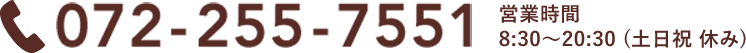飲食業界ではお米を家庭用米、業務用米と呼び分けますが、厳密にはどのように定義づけが異なるのかあまり詳しく知らないという人も多いでしょう。
この記事では業務用米とはどのようなお米か使用するメリットまで詳しく解説します。
業務用米とはどんなお米?
2018年に農林水産省が発表した農林水産(米政策)という資料では業務用米を「中食・外食でニーズがある比較的低価格の主食用米」と定義づけています。
しかしこの文言だけでは業務用米について「中食や外食でニーズのあるお米」「比較的低価格のお米」ということしかわからないので、2つの観点からもう少し詳しく見ていきましょう。
中食・外食とは
中食(なかしょく)は、一般的には「中食業」という食品産業の分野を指します。
中食業は、主に日常的な食事を提供するために調理された食品を製造・販売する業態を含みます。
中食業者は、弁当、惣菜、冷凍食品、レトルト食品などを製造し、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、駅弁など。外食(がいしょく)は、自宅や自分の通常の生活空間以外で食事をすることを指します。
外食は、レストラン、カフェ、ファストフードチェーン、居酒屋、食堂などで提供される料理を食べることを意味します。
参考:農林水産省 「農林水産(米政策)」
基準をクリアした安全で美味しい米
お米は食品なので、家庭用米でも業務用米でも等しく「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」に基づき、強制的な品質表示基準制度と任意のJAS規格制度が適用されます。
具体的には包装された玄米及び精米については、以下5点の表示が義務付けられているのです。
・名称
・原料玄米
・内容量
・精米年月日
・販売者
原料玄米の表示方法は2種類あり、単一原料米と複数原料米に分かれます。
単一原料米とは産地、品種及び産年が同一であり、証明を受けた原料玄米を用いたお米のことです。
また複数原料米とはいわゆるブレンド米のことで、複数ある原料玄米それぞれの品種や産年、どのくらいの割合で用いているのかを明記します。
このようにお米は家庭用米でも業務用米でも品質表示基準制度をクリアしないと販売することはできないので、日本国内では安全で美味しいお米が流通していると言えるでしょう。
参考:農林水産省 消費・安全局 表示・規格課「食品の品質表示とJAS規格について」
業務用米と一般的な家庭用米との違い

一般的な家庭用米と業務用米との違いはどのようなものなのでしょうか。
よく挙げられるのはお米の種類と量です。
お米の種類の違い
業務用米と家庭用米では、使用されるお米の種類に違いがあります。家庭用米は、コシヒカリやあきたこまちなどブランド米の単一原料米が多く、食味や香りを重視して選ばれます。
一方、業務用米は、ブレンド米の割合が高く、大量調理に適した粘りや粒立ちのバランスが考慮されています。また、業務用では冷めても美味しい品種や、チャーハン・寿司など料理に合わせた品種が選ばれることも特徴です。飲食店や施設の用途に最適化された米が使用される点が、家庭用米との大きな違いです。
お米の量の違い
業務用米と家庭用米では、販売される量に大きな違いがあります。
家庭用米は、一般家庭での消費を前提としており、500g・2kg・5kg・10kgなど、小分けされたサイズが主流です。
一方、業務用米は飲食店や施設での大量消費を想定し、10kg以上が基本で、20kg・30kgの大袋で販売されることが一般的です。また、仕入れコストを抑えるために、まとめ買いでさらに大容量の袋や定期購入が用意されることもあり、業務用途に適した流通形態になっています。
業務用米は粒の均一性が重視される
業務用米は、飲食店や食品加工業者が使用するため、粒の大きさや形が均一であることが求められます。
これにより、炊き上がりの見た目や食感が安定し、どの店舗でも同じクオリティのご飯を提供できるようになります。
一方、家庭用米は、個人の嗜好に合わせた幅広い品種が販売されており、多少の粒のばらつきがあっても問題になりにくいです。特に業務用では、機械での炊飯適性や大量調理に適した品種が選ばれるのが特徴です。
業務用米は炊飯適性を考慮して選ばれる
業務用米は、大量炊飯に適した品種が採用されることが多く、冷めても美味しく食べられるものが重視されます。
例えば、弁当やおにぎり用には、冷めても粘りと甘みが持続する品種が選ばれ、飲食店では、カレーやチャーハンなどに合う粒立ちの良い米が求められます。
一方、家庭用米では、個人の好みに合わせて柔らかめや硬めなどの炊き上がりを重視し、特定の料理に特化した品種選びは少ない傾向にあります。
価格設定の違いがある
業務用米は、コストパフォーマンスを重視して選ばれるため、家庭用米と比べて価格が抑えられていることが多いです。
これは、一度に大量購入されることを前提に流通しているため、1kgあたりの単価が割安になっているからです。また、品質が安定していることが求められるため、価格の変動が少なく、安定供給が可能なブレンド米が多く流通するのも特徴です。
一方、家庭用米は、ブランドや品種ごとに価格差が大きく、個人の嗜好に応じて購入されることが一般的です。
業務用米のメリット

業務用米を使用するメリットにはどのようなことがあるのでしょうか。
3つご紹介します。
比較的安価で取引できる
業務用米は比較的安価で手に入れることができます。
これは販売される時のお米の量が家庭用米と比較すると多いためだと言えるでしょう。
業務用米は大量購入や流通コスト、需要と供給のバランスなども影響して比較的安価に取引ができるといえるでしょう。
低価格ながらも良質な米
業務用米は低価格ながら、近年その品質が向上してきています。
例えば今多く収穫できて食味の良い「多収米」が業務用米の中でも注目されています。
「多収米」とは「多く収穫できるお米」のことで品種や栽培方法によって違いますが、通常は一般米よりも10%~30%多く収穫できる品種です。
多収米の作付面積は全体の3%ほどですが単一銘柄米とあまり区別がつかない食味と、10アールあたりコシヒカリが550kgの収穫となるのに対して750kgほども収穫できることに大手企業が着目し、生産量の増強を図っているため今後市場にも多く出回ることが予想されているのです。
参考:農研機構 次世代作物開発研究センター「業務用・加工用に向くお米の品種2018」
メニューや量などの需要の変化に対応しやすい
飲食店や中食業界などは日々多くのお客様に提供するので、様々な需要に対応しなければいけません。
業務用米はメニューに合わせてお米を最適にブレンドしてくれたり、仕入れの量を相談できるので使用するメリットと言えるでしょう。
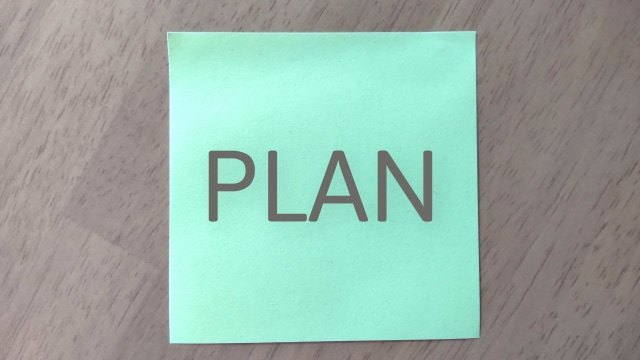
業務用米の用途
主食用米の総需要のうち4割を占めていると言われる業務用米は、どのような用途で使われることが多いのでしょうか。
2つご紹介します。
飲食店、ホテル、弁当など米の消費が多い業種・形態の外食産業が中心
業務用米は飲食店、ホテル、弁当屋など米の消費が多い業種・携帯の外食産業を中心に使用されます。
同じ外食産業とは言っても業務用米に求められるニーズはさまざまで、例えば次のようなことが挙げられるでしょう。
・おにぎり用なら形の崩れにくい米
・丼もの用なら粘り気の少ない米
・寿司用なら古米
・加工食品用なら加工方法に適した米
外食産業のお米を使用する人気メニューは、このような難しいニーズを満たす業務用米が支えているのです。
中華料理に合う業務用米とは?
中華料理は油を多く使った濃い味付けの料理が多く、ご飯はその味を引き立てつつも、口の中をさっぱりと整える役割を果たします。
そのため、粘りすぎず、程よい硬さと粒立ちの良さを備えた業務用米が適しています。チャーハンや中華丼、麻婆豆腐などと相性の良い、べたつきにくい業務用米の選び方がポイントです。
中華料理におすすめの業務用米は、やや硬めで粘りが少なく、粒が立つタイプのブレンド米です。特にチャーハンや中華丼では、ご飯がべたつくと全体の仕上がりに影響します。
中華料理店の厨房では、調理のスピードも求められるため、無洗米仕様で炊飯の効率も高めるラインナップも人気です。
和食に合う業務用米とは?
繊細な味付けが特徴の和食では、ご飯の風味や粘り、ツヤが料理全体の印象を左右します。
刺身や煮物、焼き魚といった和食においては、主役に寄り添う香り高くふっくらとした炊き上がりのご飯が求められます。
和食に合う業務用米は、ほどよい粘りと甘みがあり、冷めても硬くなりにくい米が最適です。出汁や素材の味を大切にする和食には、ご飯そのものが主張しすぎず、しかし存在感のある米が欠かせません。また、弁当や定食用に冷めても美味しさが続く品種も人気です。
粘り・風味・安定供給のバランスに優れた米で、和食の味をより引き立てます。
おにぎりに合う業務用米とは?
おにぎりは、ご飯そのものの味や食感がダイレクトに伝わるメニューのひとつです。
そのため、粘り・握りやすさ・冷めた時の美味しさが非常に重要です。飲食店やテイクアウト専門店、コンビニなどで多く利用されるおにぎり向けの業務用米には、特有の条件が求められます。
焼肉に合う業務用米とは?
焼肉店では、ジューシーで脂の多い肉に負けない、存在感のあるご飯が求められます。
お肉の旨味を引き立てつつ、食べ応えのあるご飯を提供するには、しっかりとした食感と粒立ちの良さを備えた業務用米が最適です。
焼肉と相性の良い業務用米は、やや硬めで粒が立ち、肉の油分をしっかり受け止められる力強さのある米です。
焼肉との相性を考え、あえてもっちりしすぎない米を選ぶことで、お肉の味が引き立ち、ご飯が進みます。また、丼物や定食にも使いやすく、幅広い焼肉メニューに対応できるのが特徴です。
米の仕入れ→炊飯→消費者に提供するスタイル
また定食屋、ファミレスなどの業態ではお米で何か料理を作るのではなく、仕入れた業務用米を炊飯して消費者にそのまま提供するという用途もあります。
お米の味が直接メニューへの評価につながることもありうるため、どのような業務用米を選択するかは慎重に行う必要があるでしょう。
業務用米をおいしく炊くコツ
以下のようなことに注意すると良いでしょう。
- お米の粒がそろっていることや割れていないことを確認すること
- 水はミネラルウォーターや浄水器の水が理想ですが、コスト面で難しい場合はプリタなどの浄水器を取り付けること。
- 浸水に使う水は低温のものが良く、あまり長く浸水させないこと。60分程度が理想ですが、あまり浸水時間が長すぎるとお米がべたつく原因になるので注意が必要です。
- 保温は4時間ぐらいまでにすること
業務用米の品質を安定させるための管理ノウハウ
業務用米は、安定した品質を維持できるかどうかが、料理の味や提供品質を左右します。特に飲食店や介護施設、給食現場では、炊き上がりのブレや風味の低下がクレームや満足度低下につながるため、日常的な管理が重要です。
ここでは、炊飯水の管理方法、季節ごとの保存・保管の基本、品質が落ちやすい条件への対策、焼け米や虫の発生を防ぐ現場での実践的なポイントを整理し、業務用米の品質を安定させるためのノウハウを紹介します。
炊飯水の管理で味のブレを防ぐポイント
業務用米の品質を安定させるには、炊飯水の管理が欠かせません。水質や水温が一定でないと、炊き上がりに差が出やすくなります。
管理のポイント
- 使用する水はできるだけ同一水源に統一する
- 冷水・温水の混在を避け、水温を一定に保つ
- 浄水器を導入し、塩素や不純物の影響を軽減
- 無洗米は普通米より加水量をやや多めに調整
これらを徹底することで、日々の炊飯品質を安定させやすくなります。
保存・保管の基本|季節ごとの温度・湿度管理
精米後のお米は、季節によって劣化スピードが大きく変わります。業務用では特に保管環境の見直しが重要です。
季節別の管理ポイント
- 春夏:高温多湿を避け、冷暗所または冷蔵保管
- 秋冬:乾燥しすぎないよう密閉容器で管理
- 直射日光や厨房の熱源付近を避ける
- 床置きせず、棚やパレットで湿気対策
温湿度を意識した保管が、品質劣化の防止につながります。
品質低下・焼け米・虫を防ぐための現場対策
お米の品質は、管理環境次第で急激に落ちることがあります。特に焼け米や虫の発生は、業務現場で避けたいトラブルです。
現場で実践したい対策
- 長期保管を避け、適正量を小分けで精米
- 高温状態が続く場所での保管をしない
- 米びつは定期的に清掃し、古米を残さない
- 唐辛子・防虫剤などを適切に併用
- 異臭や変色があれば早めに仕入れ先へ相談
日常管理を徹底することで、品質トラブルの予防につながります。
まとめ
業務用米は外食産業・中食などで消費される比較的安いお米を指しますが、近年はさらに食味が良くなりメニューに合わせて最適に品種のブレンドされたお米が登場するなど、良質で使い勝手の良いお米となっています。
業務用米の特徴とメリットを理解した上で、自分の作りたい料理に合ったお米を手に入れるようにしましょう。