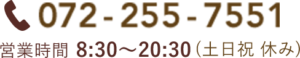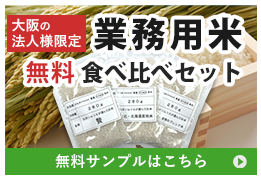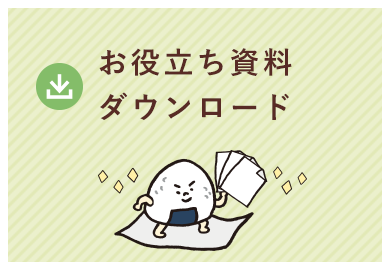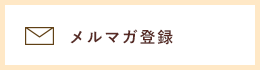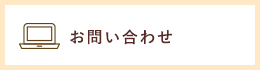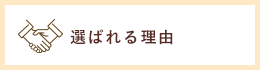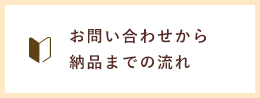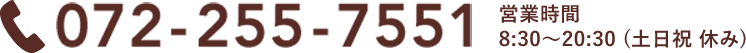新米と古米とは何か?
新米、古米とよく言われますが、その区別や特徴はどこにあるのかについてまず見ていきます。
いつまで新米なのか、いつから古米なのかを参考にしてください。
新米とは、収穫後に乾燥させたばかりのお米で水分が多め、香りや甘みが豊か
食品表示法では、「新米」と表示できるのは、収穫された年の12月31日までに精白または包装されたお米に限られます。
一方、米穀年度(11月1日~翌年10月31日)による定義では、その期間中に収穫されたお米が「新米」とされます。
つまり、カレンダー年と流通年度の両面から判断される、二重の定義が存在します。
収穫後に乾燥させたばかりのお米のため水分が多く、香りや甘みが豊かなのが特徴のお米です。
たとえば 「2025年度の新米」 とは、以下のように判断されます。
食品表示法(JAS法)による定義:2025年に収穫された玄米または精白米が、同年の12月31日までに精白または包装されていれば「新米」と表示可能です。
米穀年度による定義:2024年11月1日~2025年10月31日の間に収穫されたお米も「新米」と扱われます。
つまり2025年10月までに収穫されたものは米穀年度上の“2025年度新米”、2025年12月末までに精米・包装されたものは表示上“新米”となります。
古米とは、収穫後に時間が経ったお米で水分が少なめ、香りや甘みが落ちる
一般には収穫から1年以上経過したお米が「古米」と呼ばれます。
ただし、米穀年度ベースでは収穫翌年の11月1日以降に「古米」と見なされる傾向があります。
食品表示法の観点では「新米」表示対象外になった時点で「古米」と判断されることもあるため、古米の定義には収穫時期と表示時期の両面を考慮する必要があります。
収穫後に時間が経ったお米のため新米よりも水分が少なく、香りや甘みが落ちます。
新米と古米の水加減の基本
新米と古米を炊く際には水加減が異なりますので、詳しく紹介します。水の分量について知っておくことでおいしいご飯が炊けておすすめです。
新米と古米では、お米の水分の量が違う
新米と古米では、お米自体の水分量が異なるのが特徴です。古米になると、水分が減りますので、多めの水で炊くことが大切です。逆に新米は、水分がありますので、水を控えめにすることでおいしいご飯が炊けます。
新米の水加減は、一般的にはお米1合に対して水150ml程度が目安
一般的にお米1合150ml(150g) に対して、 水 210ml(210g)が適量です。
新米の場合は水を控えるようにし、水200ml(200g)程度で大丈夫です。
新米は水分が多いため、いつも通りに炊くとべちゃっとしたお米になるため、3割程度控えるといいでしょう。
古米の水加減は、一般的には、お米1合に対して水220~230ml程度が目安
古米を炊く場合は、お米1合150ml(150g) に対して、水220ml(220g)~230ml(230g)がおすすめです。
通常よりも多めに水を入れて炊いてください。
いつもより1割増しほどで炊くことで、古米もふっくらしたご飯になっておすすめです。
新米と古米の水加減のコツ
新米と古米の水加減のコツについて具体的に見ていきますので、参考にしてください。
新米と古米の水加減は、炊飯器のいつもの目盛りよりも加減して炊くことで美味しく炊けるでしょう。
また、他にも水加減のコツがあるので知っておくといいでしょう。
新米と古米の水加減は、基本の目安から微調整することで、よりおいしいご飯に
新米の場合は、目盛りよりも少し下になるように調整すると大丈夫です。
古米の場合は、目盛りよりもほんの少し上に入れるのがコツです。
古米の年数によって水加減は調整してください。
また、それ以外にも新米や古米を上手に炊くコツがありますので、参考にしてください。
新米は水の量を少なめ。お米を30分水に浸すことで水分が均一に
新米の水の量は少なめに炊きますが、水に浸す時間も気を付けることが大切です。30分程度であまり長く水に浸さないようにしてください。
新米を長く水に漬けておくと、でんぷん質が溶け出してべちゃっとした食感になってしまいますので、気を付けるのがコツです。
古米は水の量を多め。炊飯前に、お米を3回程度洗うことで、ふくらみやすい
また、古米は水の量を多めにし、炊く前にお米を良く洗うことが大切です。
古米の場合、古米臭がありますので、それを取るために3回程度洗うのがおすすめです。
そして、古米は表面が乾燥していますので、通常の倍の1時間~2時間程度浸水することで、古米に水をよく吸水させてふっくら炊くといいでしょう。
新米と古米の水加減を変えるタイミング
新米と古米の水加減が異なりますが、どのタイミングでいつまで水加減を変えればいいのかについても見ていきます。
新米と古米の水加減は、季節や気温に影響
新米と古米の水加減は、季節や気温に影響を受けます。例えば、夏の場合は水温も温かくなります。
お米を炊く際には、冷たい水から高温に一気に炊き上げることで美味しくなります。
新米の時期はあまり寒くないため、水が温かい場合は、お米1合に2~3個の氷を入れて炊くのもいい方法です。
新米の収穫は9~11月頃。12月末までは新米の水加減
いつまで新米と呼ぶのかですが、その年のお米が収穫されるのが9月~11月で、12月末までは新米と言えます。
12月末までは水加減を少なめにしておくといいでしょう。
1月からは乾きが出るので、水の量を少し増やそう
そして、翌年の1月からは冬の寒さもあり、お米の表面が乾いてきます。
水の量を少し増やすようにし、炊飯器の目盛り通りに炊いて大丈夫です。
古米は、5月になると外気温が高くなりさらに乾燥。水の量をさらに増やそう
古米の場合は、5月頃の暖かい時期により表面が乾燥します。
さらに水の量を増やして炊く方法がおすすめです。
水温も高くなりますので、氷を入れて炊くのもいい方法です。
古米の保管は冷暗所&密閉保管などで保存
古米は、表面が乾燥して味が落ちていきますので、保管の際は冷暗所や密閉保管などをするといいでしょう。
特に夏などは気温や湿度などに気を付けて保管するようにしてください。
まとめ
新米の水加減をいつまでするのかなどについて見てきました。
新米は、水を控えて炊くことが大切です。特に9月~12月までは新米の水加減を控えるといいでしょう。
しかし、それ以降はあまり気にする必要がないとも言えます。
また、新米から1年経った11月頃から古米と呼ばれます。
古米を美味しく炊くには水を1割増しで炊くといいでしょう。
水に1~2時間程度浸けておき、3回程度洗い、水を多めにして炊くことでふっくら炊けます。
新米と古米の水加減をいつまで調節するのかなどを知って、炊き方のコツを覚えることでいつでもおいしいご飯を炊いてみませんか。