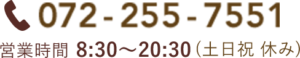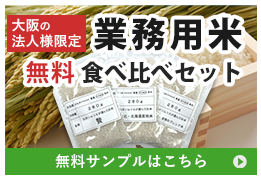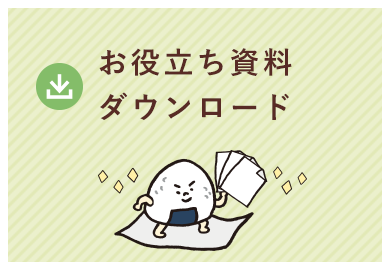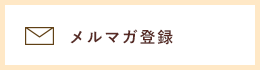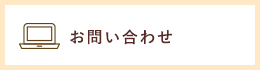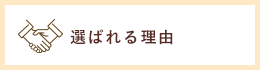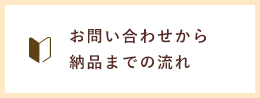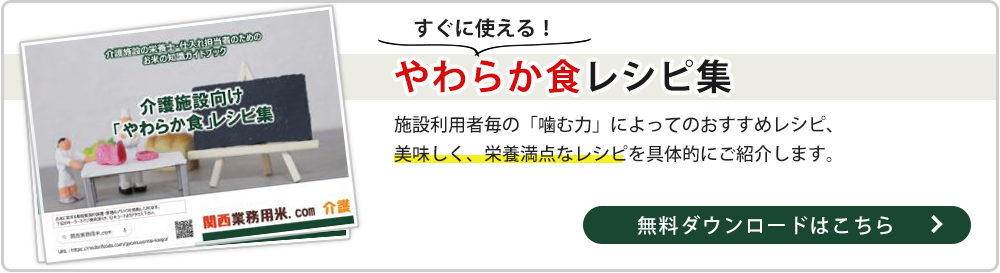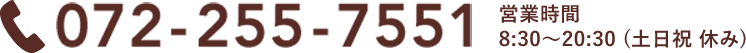病後の高齢者のためには介護食の中でも流動食が食べやすいと聴くけれど、具体的にどのような食事なのかや作り方がよくわからないと悩んでいる人はいませんか?
この記事では流動食が必要な理由から作り方のポイント、レシピまで詳しく解説します。
なぜ、流動食?
介護食の中でもなぜ具なしの野菜スープ、重湯、ジュース、牛乳、くず湯などを利用した流動食なのか、理由を2つの観点から説明します。
咀嚼や嚥下機能の低下
そもそも流動食とはどのような食形態を指すのでしょうか。
流動食とは、液状になっていて噛まなくても食べられる食事のことで、これを「普通流動食」と言います。
そしてチューブやカテーテルなどを用いて胃や腸に直接栄養を流し込む胃ろう、腸ろうなどの経管栄養にも流動食が用いられる場合がありますが、1mlあたり1kcal以上のエネルギーを摂取することができるため、これを「濃厚流動食」と呼びます。
また腎臓病や循環器疾患など特定の疾患に対応しているのが「特殊流動食」です。
普通流動食は病院からの退院直後に通常食への移行を目的に用いたり、飲み込む力が弱い人向けの介護食として提供されたりすることが多いでしょう。
濃厚流動食は誤嚥などで口から食事をするのが困難になった人が胃や腸から直接栄養を取りこむのを目的として用いられ、看護師や介護福祉士の有資格者、または一定の研修を受けた介護職員のみが経管栄養を行うことができます。
普通流動食でも濃厚流動食でも、口から栄養を摂取するのに咀嚼や嚥下など、何らかの問題を抱えている場合に用いられることを覚えておきましょう。
参考:一般社団法人日本流動食協会「流動食の使い方」
参考:北区障碍者地域自立生活支援室「介護職員が行える医療的ケアの範囲」
消化吸収が良い
高齢者の場合、そもそも栄養の消化吸収能力が衰えています。
このため同じ高齢者でも点滴栄養、経管栄養、食事の3つの方法で栄養を取ると、食事では体重が増えることがあっても経管栄養では維持するのがやっとで、点滴栄養では体重は低下してしまうことが多いのです。
このことから液状で消化吸収が良く口から食べることのできる流動食は、高齢者にとってメリットの大きい食事だと言えるのです。
普通・濃厚・特殊流動食とは?3タイプの違いと用途比較
流動食には、患者さんの状態や栄養ニーズに応じて「普通流動食」「濃厚流動食」「特殊流動食」といった種類があります。
これらは形状や栄養密度、調理法などが異なり、特定の医療・介護状況に最適な選択が求められます。
ここではそれぞれの特徴と使用シーンについてわかりやすく紹介します。
普通流動食:術後や経口摂取再開時のスタンダード
普通流動食とは、固形物が食べられない時期に適した流動性のある食事形態です。重湯(おかゆの上澄み)や具のない野菜スープ、果汁やスムージーなどが含まれます。消化に負担をかけず、水分補給も兼ねているため、術後や絶食期間の回復期に用いられることが多く、段階的に食事へ移行するためのベースとなるメニューです。
介護現場でも初期段階でよく使われます。
濃厚流動食:少ない量で高栄養を補給できる
濃厚流動食は、1ミリリットルあたり少なくとも1キロカロリー以上と、高いエネルギー密度が特徴です。プロテイン、ビタミン、ミネラルをバランスよく含み、十分な栄養を少量で摂取できるため、食欲が低下している方や高栄養補給が必要な場面に適しています。
ただし、とろみがあり消化しやすい反面、下痢など消化器への負担が出ることもあるため注意が必要です。
特殊流動食(嚥下障害・医療対応タイプ)
嚥下障害のある高齢者や、特定の病気により食事制限が必要な方に使用されます。とろみの調整や栄養成分の特別配合がなされており、嚥下事故を防ぎつつ安全に栄養を摂取できます。IDDSI(国際嚥下食基準)に基づいて分類されるケースもあります。
流動食づくりにミキサーが活躍
家庭で介護食としての流動食を作るなら、どのようなレシピにおいても必ず準備しておきたいのがミキサーです。
ミキサーの中でも介護食における流動食を作るのに便利なのが、食材を細かく粉砕するミル機能と液体とともに入れた個体を粉々にして撹拌するミキサー機能を兼ね備えたミルミキサーです。
付属のオプションや機能に応じて価格が2,000円~20,000円程度と幅がありますが、本格的なレシピで流動食作りに取り組むならぜひ1台準備しておきましょう。
このように便利なミルミキサーを使用して作った介護食における流動食には、どのような特徴があるのか3つご紹介します。
とろみ
やわらかく煮た食材などとゲル化剤などを一緒にミルミキサーにかけると、簡単に流動食にとろみをつけることができます。
流動食にとろみを少しつけるだけで、高齢者の人にとっては喉の中ですべりが良くなり、誤嚥を防ぐことにもつながるでしょう。
野菜がたっぷり
ゆでた野菜を個別にミルミキサーにかけて流動食にすると、食感などからあまり野菜を好まない高齢者の人でも意外と食べてくれることが多いものです。
見た目がスープのように見えるため「野菜をたくさん食べなければ」というプレッシャーからも解放されやすくなるのが流動食のメリットだと言えるでしょう。
栄養バランスが◎
介護食における流動食では、肉・野菜・魚と少しずつの量をミキサーにかけて栄養バランスのよいメニューにすることができます。
一品食いなどの癖がある人でも、ボリューム自体がそれほど多くないためお米だけを残したり、おかずだけを残したりするといったことが少なくなって全量を食べてくれることから、自然に栄養バランスが保たれるのです。
お手軽な流動食介護食レシピ

「秋のきのこのクリームスープ」
旬のきのこを用いた介護食における流動食レシピ「秋のきのこのクリームスープ」をご紹介します。
材料(1人分)
・軸や石づきを取り除いたしいたけ(40g)
・エリンギ(10g)
・しめじ(10g)
・玉ねぎ(1/4)
・じゃがいも(1/4)
・バター(4g)
・コンソメ(適量)
・水(具材がひたひたになる程度)
・牛乳(100ml)
・生クリーム(20ml)
・黒こしょう(適量)
・塩(適量)
・パセリ(適量)
作り方
①きのこ、じゃがいも、玉ねぎを小さめに切っておく
②玉ねぎをこがさないように気を付けながら炒める
③きのことじゃがいもを追加して火が通ったらコンソメを入れる
④水をひたひたに入れてじゃがいもが柔らかくなるまで煮る
⑤火を止めて粗熱を取ったら牛乳を加えてミルミキサーにかけ、ペースト状にする
⑥ペースト状になったら再び火にかけ、味を見ながら生クリームと塩で調整する
⑦パセリを散らして完成
野菜と豆腐のなめらかポタージュ
材料(2人分)
- にんじん 50g
- かぼちゃ 50g
- 絹ごし豆腐 100g
- 牛乳(または豆乳) 200ml
- 塩 少々
作り方
- 野菜を柔らかくなるまで煮る。
- 豆腐と一緒にミキサーにかけてなめらかにする。
- 牛乳を加えて温め、塩で味を調える。
ビタミンとたんぱく質をバランスよく摂れる介護向け流動食です。
鶏ささみと米のおかゆスープ
材料(2人分)
- 炊いたご飯 100g
- 鶏ささみ 50g
- にんじん 30g
- 水 300ml
- しょうゆ 少々
作り方
- 鶏ささみとにんじんを柔らかく煮る。
- ご飯を加えてさらに煮込み、全体をやわらかくする。
- ミキサーでなめらかにし、しょうゆで軽く味を整える。
タンパク質と炭水化物を一度に摂取でき、体力回復に適した一品です。
まとめ
流動食は「普通流動食」「濃厚流動食」「特殊流動食」の3種類があり、家庭で介護食として用いられるのは普通流動食であることがわかりました。
ぜひミルミキサーのように便利な道具も駆使して、楽しみながらさまざまなレシピで流動食を作ってみてください。
関連記事:【ユニバーサルデザインフードとは?】介護食の区分と作り方
日本介護食品協議会HP 「ユニバーサルデザインフード」参照
https://www.youtube.com/watch?v=607nlL29meI